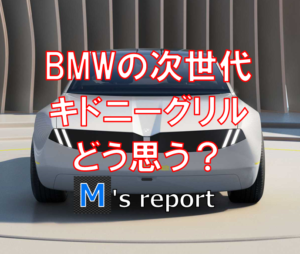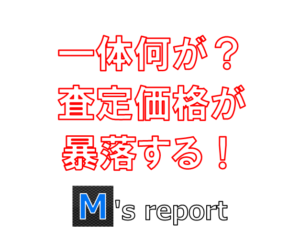2020年頃から輸入車を中心に、リアバンパーにあったはずのものが無くなっています。
それはマフラーエンドです。
車を後ろから見たら必ずあった排気ガスの出口、マフラーエンドがなくなっています。
マフラーエンドの形状や大きさで車の性能が想像できるほど、車にとってマフラーエンドは必要なものだったはずです。
そして、マフラーエンドの代わりに採用されたものが、ダミーマフラーです。
フェイクマフラーとも呼ばれています。
つまり、マフラーエンドの形をした飾りのことです。
今回は、車の印象やキャラクターを左右するほど重要な存在だったマフラーエンドがダミーマフラー(フェイクマフラー)になった理由を考えてみたいと思います。
覆面パトカーの見分け方⇒覆面パトカーの見分け方って何?車種?アンテナ?ナンバープレート?
[getpost id=”7787″]
ダミー(フェイク)マフラーが採用される理由とは?
ダミーマフラーが採用されている理由を考えましょう。
ここでは約20年間身を置いた元自動車営業マンの勘と経験をフルに活用して持論を展開していきます。
理由①デザイン優先
ダミー(フェイク)マフラーが採用されるようになった背景には、メーカーがデザイン優先になってきたことが考えられます。
車を後ろから見たときにマフラーが大きかったら「スポーティ」であったり、「速そう」といった印象を受ける人は多いと思います。
もちろん、私もその一人です。
メーカーのデザイナーも一台一台の性質に合ったマフラーエンドをデザインすることで、個性を演出していました。
しかし、私が営業マン時代にこんな声も多かったです。
そうなんです!小排気量エンジンが搭載される車の多くは、マフラーエンドが片側からの1本のみになっていました。
車好きからすると、マフラーエンドは左右から2本出ている方が速そうに見えるからその方が嬉しいはずです。
マフラーエンドが2本出しになっている車のほとんどは2.0ℓ以上のエンジンが搭載されています。
しかし、2010年頃から輸入車を中心にダウンサイジングターボエンジンが採用され始めました。
排気量は2.0ℓから1.8ℓになり、さらに1.5ℓ、そして今では1.0ℓモデルまで登場しています。
小排気量のエンジンに不必要な排気効率のマフラーを装着すると加速力が鈍るため、ほとんど車種のマフラーは1本出しになるのです。
そこでメーカーが考えたのがダミー(フェイク)マフラーだったのでしょう。
リアバンパーにダミー(フェイク)マフラーをデザインすることで、どんなに小排気量のエンジンだろうと関係なく2本出しマフラーのように見せることが出来るわけです。
さらに、ダミー(フェイク)マフラーにすることで、「ベースモデル」「売れ筋モデル」「スポーティモデル」を異なるデザインにすることで差別化も図ることが出来ます。
ダミー(フェイク)マフラーが採用された理由をデザインを優先したため考えると、確かに一理ある気がします。
理由②コストダウン

ダミー(フェイク)マフラーが採用されるようになった理由に、コストダウンが関係していると思います。
2000頃までは、ほとんどのメーカーで車種ごとに専用のシャシーを開発やエンジンを開発していました。
ところが、2010年頃からは、ドイツ車を中心に「スモールカー」「ミディアムカー」「ラージーカー」の区分ごとにプラットフォームを作って、あとは組み立てるだけというモジュール方式が採用されるようになりました。
モジュール方式により、車の開発はもとより、製造においても大幅にコストダウンすることに成功しています。
マフラーにも同じことが言えます。
車種ごとに異なるマフラーエンドをデザイン、そして製造するとそれだけコストが掛かります。
ダミー(フェイク)マフラーを採用することで、そもそも個別にマフラーエンドをデザインする必要がなくなります。
つまり、1つのマフラーでどんな車にでも採用することが出来るというわけです。
ダミー(フェイク)マフラーの採用は、年間に万枚台という車を製造するメーカーにとっては願ってもないコストダウンになったことでしょうね。
コストダウンされた費用は、貯金に回されています。というのは冗談ですが、より良いシステム開発のための原資に使われているはずです。
ダミー(フェイク)マフラーが採用されコストダウンしたことが、私たちへ安全な車という形で還元されていると思えば少しは納得できるかもしれません。
理由③電気自動車の存在
ダミー(フェイク)マフラーが採用されるようになった理由は、電気自動車の存在が大きいと思います。
2020年以降、世界中の自動車メーカーが目の色を変えて電気自動車の開発と発売に躍起になっています。
ほとんどの欧州メーカーは2025年というリミットを定め、出来るだけ早い電気自動車社会への移行を推し進めています。
実は、欧州メーカーの電気自動車への移行計画は2010年頃から進められていました。
つまり、欧州メーカーはガソリン車と電気自動車が混在する未来を見据えていたということです。
電気自動車はガソリン車のように排気ガスを発生しません。
よって、マフラーが存在しないため、車の後ろにはマフラーエンドも存在しないのです。
ということは、マフラーエンドがあるガソリン車に乗っていたら、一目でガソリン車って分かってしまうというわけです。
もし、ガソリン車を良しとしない社会になっていたら?
もし、ガソリン車が差別される社会になっていたら?
マフラーエンドがあることで、ガソリン車と指をさされて嫌な思いをするかもしれない・・・・とちょっとオーバーに考えましたが、可能性はゼロではありません!
2020年頃から新車にダミー(フェイク)マフラーが採用されるようになった理由の1つに、ガソリン車と電気自動車の見た目の違いをなくしたいという意図があると思います。
内燃機関(ガソリン車とディーゼル車)と電気自動車の両方にダミー(フェイク)マフラーが採用されれば見た目による偏見や劣等感は生まれにくいですからね。
2022年までに開発が進められている高性能電気自動車にもダミー(フェイク)マフラーが採用されています。
つまり、電気自動車のデザイナーも「大きいマフラーエンド=速い車」という印象は変わらないようです。
高性能電気自動車①⇒【レクサス次期新型LFA】電気自動車で復活!2秒で時速100kmに到達する世界を味わえる!
高性能電気自動車②⇒【試乗レビュー】アウディRSe-tronGTインプレ&評価!5つの気になる点とは?
[getpost id=”7458″][getpost id=”7046″]
ダミー(フェイク)マフラーってダサい?
多くの新型車に採用されているダミー(フェイク)マフラーについて「ダサい」という言葉を耳にします。
個人的な見解だと、ダサくはないと思いていますが、残念な気持ちがあります。
私も車好きとして、マフラーエンドが本物でないことは寂しいですね。
しかしながら、本物のマフラーがあったらあったで「見た目はカッコいいのにマフラーが小さい」とか、「マフラーが左右2本出しだったらなぁ」とか思ってしまいます。
それならいっそのこと、「マフラー見えんくしたらええやん!」って思います。
排気量の問題で左右2本出し出来ないモデルはダミーマフラーを採用して、そもそも2本出し出来るモデルは本物のマフラーが理想ですよね。
ダミー(フェイク)マフラー自体よりも、リアバンパーに大型のマフラーエンドが採用されていて、奥の方でバカみたいに小さい本物マフラー見えていた方がダサくないですか?
もちろん、ダミー(フェイク)をダサいと思うかどうかはあなたの自由です。
ただ、ダミー(フェイク)マフラーの理由を少しだけ考えたら、少しは納得するかもしれませんよ。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
アウディ次期新型SQ5をスクープ!フェイクではなくリアルマフラーを採用!
ディーラーに行く前に査定をしよう!
お目当ての車が決まったらディーラーに行く前に査定をすることをお勧めします。
査定をする理由は、今のあなたの愛車の価値(査定価格)を知ることができるからです。
新車の納期が延びたことにより、ディーラーでは数カ月後の納車まで査定価格を保証して契約を行うケースが増えています。
査定価格を保証してくれるのはとてもありがたいことですが、その査定額が「高い」のか「安い」のか、あなたは分かりますか?
元自動車営業マンからすると、保証されている査定価格は「数カ月後に予想される最低限の査定価格」である可能性もあると思います。
つまり「このくらいの価格なら間違いないだろう」という価格かもしれないのです。
もちろん、あなたがその査定額に満足し、納得するのであれば問題ありません。
しかし、あなたが今のあなたの愛車の本当の価値(査定価格)を知っていれば、査定価格をもっと高く出来るかもしれないのです!
あなたの愛車の本当の価値を知ることは、あなたにとってプラスでしかありません。
あなたの次の愛車選びを満足いくものにするため、あなただけが損をしないため、ディーラーに行く前に査定をしてあなたの愛車の価値を知ることは重要なことなのです。
愛車の査定は定期的にすることがコツ!
あなたの愛車を高く売るコツは定期的に査定を行い「売り時」を見定めることです。
中古車市場は需要と供給によって価格相場が変動します。
あなたの愛車の査定価格が一番高い時期、もしくは、下げ幅が小さい時期を見計らうことが大切です。
とにかく一度、あなたの愛車の価値を知るために査定価格を知ることを強くお勧めします。
査定価格を知ることによるメリットは以下の通りです。
●愛車の査定額の適正価格を知るため
●愛車の「売り時」を見極めるため
●最小限のお金で色んな車に乗るため
●ディーラーとの交渉を優位に進めるため
●あなただけが損をしないため
今現在、あなたが愛車を手放す予定がなくとも、現在のあなたの車の価値(査定額)を知っておくことは決して損ではありません。
今後の車の買い替えの際に参考になることは間違いありません。
とにかく査定結果を見て、納得すれば手放して現金化すればいいし、納得しなければ乗り続ければいいだけです。
現在のあなたの車の価値を知るために利用してみるのも有りだと思います。
あなたが想像している以上の買取額が提示されるかもしれませんよ。
あなたの愛車の査定額をチェックしよう!
まずは、あなたの愛車の査定額をチェックしましょう!
無料査定のサービスを活用すれば、ディーラーの査定では5万円だった車が、15万円アップの20万円に!
150万円の車が50万円アップの200万円に!
もしかすると、200万円だった車が250万円以上になる可能性もあるかもしれません!
今は自動車ディーラーや中古車販売店での高額値引きは期待できません。
値引きが期待できない以上、車を出来るだけ安く購入するためには、あなたの愛車の査定額を最高額にする必要があるのです。
買取店を一軒一軒回ってもいいでしょうが、そんな面倒で時間のかかることをしなくても最高の査定額を手に入れることが出来ます。
最大20社をWEBだけで比較!“2度目に選ばれる”中古車買取一括査定【MOTA車買取】であなたの愛車を査定してみてください。
MOTA車買取は、しつこい営業電話が一切ない無料の一括査定サービスです。
あなたの愛車の情報を登録すると、最大20社からの査定額入札が開始されます。
査定額は登録したメールアドレスで確認することが出来、最高額を入札した上位3社のみがあなたへの交渉権を獲得することが出来ます。
だから、しつこい営業電話であなたの仕事中やプライベートを邪魔されることはありません!
査定は3社とも同じ日同じ時間を指定してください!
そうすることで、たった1回の査定(時間にして20~30分程度)で最高額を知ることが出来ます!
各社の担当者を同時に競わせることで買取価格の底上げを図る狙いもあります。
査定が終われば、各社の担当者が名刺の裏にあなたの愛車の査定額を書いて渡してくれるので、あとはじっくり価格を見て考えてみましょう。
価格に納得すれば、最高額を付けた担当者に電話して話を進めても良いし。
価格に納得いかなければ、断っていただいても結構です。
もちろん、売っても売らなくても無料なので、安心して判断してください。
私自身もMOTA車買取査定を利用してディーラーの下取価格と比べて35万円アップに成功しました!
レビューしているのでぜひ参考にしてください。
買取査定レビュー⇒【査定レビュー】高額買取に必要なのは競合させること!私は一括査定で35万円アップに成功した!
●45秒カンタン登録
●最大20社による査定額をネットで確認
●上位3社からの連絡のみ
●一回の査定で最高査定額がわかる!
車を購入する予定があろうがなかろうが、今現在のあなたの愛車の価値を知ることは大切です。
あなたの愛車はあなたの大切な財産です!決して面倒くさいからと言って軽んじてはいけません!
査定が5万円アップすれば、家族でおいしい焼肉が食べられます。
査定が10万円アップすれば、ちょっと奮発して遠くに遊びに行けるかもしれません。
査定が20万円アップすれば、行きたかった海外旅行や欲しかったものが買えるかもしれません。
査定が30万アップすれば、諦めていた上位グレードの車を検討することも出来るでしょう。
車を売買する予定がなくても、あなたの愛車の現在の価値をMOTA車買取で知ることによって、あなたの車人生が大きく変わる可能性があります!
MOTA車買取では、一般相場よりも高額で買い取った実績があります!
とにかく、売る売らないは別としてあなたの愛車を査定してみることから始めましょう。
あなたが思ってもみなかった驚きの査定額が提示されるかもしれませんよ。
思ってもみなかった査定結果に、次は何の車を買おうかなぁとワクワクしながら色々な車を検索している日々が待っているかも?
●45秒カンタン登録
●最大20社による査定額をネットで確認
●上位3社からの連絡のみ
●一回の査定で最高査定額がわかる!


 画像引用元:
画像引用元: 画像引用元:
画像引用元: